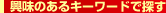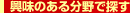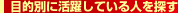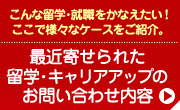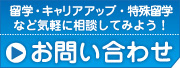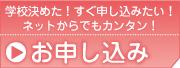|
「ガーデンシティ(庭の街)」と呼ばれる南島のクライストチャーチ。この溢れんばかりの緑に包まれた美しい街並を見渡せる丘に住む安井静香さん。その住まいは、静香さんたちご夫婦によって自由に思いのまま設計デザインされている。日本の建築士の彼女が、ニュージーランドを活躍の場とし、ミクスト・カルチャーを交えた満足ある空間を提供している。
 |
1972年生まれ。東京出身。日本大学生産工学部建築工学科卒業。1級建築士。大学卒業後、大手ハウスメーカーに勤める。1999年にワーキングホリデーでニュージーランドへ。クライストチャーチで1ヶ月間語学学校に通った後、この学校の姉妹校のデザイン&アートカレッジで2ヶ月間3DのArchiCADを学ぶ。その後、現在の夫であるボブさんの建築事務所へ。ADNZ(Architectural designers New Zealand INC) Associate member。現在妊娠中で今年1月出産予定。
|
行動することが希望につながる

日本で大学の建築工学科を卒業後、ハウスメーカーに入社しました。ここでの仕事はあまり自由がなかったため、働きながらもずっと意匠系の会社に興味を抱いていましたね。このハウスメーカーに4年半勤めた後、ずっと海外に憧れていたということもあり、1999年にワーキングホリデーを利用してニュージーランドに来たんです。他の国を選ぶこともできましたが、過ごしやすい気候で、物価も安いという理由からこの国に決めました。最初に住む街をクライストチャーチに決めたのは、雑誌などで見て、美しい場所だなとずっと気になっていたからでした。
それから1ヶ月間、現地の語学学校に通いました。その時偶然にも、この語学学校の姉妹校でデザイン&アートカレッジがあることを知ったんです。語学学校の先生の勧めもあり、その学校で3D CAD(3D computer aided design、コンピューターを利用しての三次元の設計)を学べるかどうか面接を受けることになりました。その時、建築学科の女性ディレクターがインタビュアーで、「インテリアデザインには女性がたくさんいるのに、建築となるとどうして女性が少ないんだ!」ということで意気投合し、建築学科の3D CAD(Archi CAD)に2ヶ月間特別に入れてもらえることになりました。
現在私の夫であるボブは、当時この学校の講師で、ここで初めて彼と出会いました。当時、私は今と比べるとかなり英語のハンディキャップがあったので彼に教えてもらったり、逆に彼は日本建築に興味を持っていたので、私が経験してきたことを教えたり、互いに影響をし合いました。その後、ボブはすでに個人で建築事務所を構えていたので、私はそこでお手伝いをすることになりました。いつの間にかニュージーランドで、そして自分が求めていた意匠系事務所で働けることになったのです。その頃から今まで、彼とはずっと一緒に仕事をしています。
一つの仕事が一年以上
私が感じる住宅建築のおもしろさとは、お客様によっていろいろな好みがありますがその好みを感じ取り、自分のフィルターを通して、その理想と一致させるというところではないでしょうか。やはり、家は一生の大きな買い物ですので、そこには個人それぞれの夢や要望などがたくさん詰まっているんです。打ち合わせで、お客様がご希望条件を話されている時は本当に目がキラキラしていて、そして中にはついつい思いが先走って余分な条件まで出してしまう方も少なくありません。直接目の前で話を聞くので、その思いはひしひしと伝わってきますし、私達の士気もぐんぐん上がって行くんです。いろんな制約がある中で、どれだけできるか。優先順位をもうけ、出来る限り希望を盛り込んだプランを立てていきます。
私達に依頼してくれるお客様は皆、「一生満足できる家を建てたい」という思いの方が大半で、家が完成するまでにはそれなりの長い時間が必要となります。もちろんその方とも長い付き合いになりますが、最初から不思議とフィーリングが合う方が多いような気がしますね。コンセプトデザインを作成しはじめてから、工事の着手まで約1年を要しますが、各条件もお客様によりけりですから、臨機応変に対応していかなければなりません。お客様との打ち合わせは、時に何時間もかかることや、深夜になってしまうということもあります。もちろんすんなりとはいかず、1歩進んで2歩下がるといったことも多いです。現在は妊娠10ヶ月目なので仕事はスローダウンしていますが、こういった仕事上、休みたい時に休めないことも多々あります。私はつわりが長く2ヶ月間くらい続いたのですが、具合が悪く寝込んでいた時もベッドの中で仕事のEメールや作業をしていた時もありました。
建築士としての本来は、設計や工事監督、管理などを行うことですが、顧客には外(家)と中(室内の装飾)が伴っていないといけないという強い意識があるんですね。ですので、インテリア関係の店にお客様と一緒に見に行ったり、私がその方の趣味に合わせて選んで来たりするなど、自分達ができる限り協力し、トータルコーディネイトを行っています。
キウィとの仕事は自分に合っている

ニュージーランドでは、5%の家が建築家/建築デザイナーによってデザインされた家といわれています。やはり大半はハウジングカンパニーによる建売住宅です。日本ではデザイン住宅はブームでもあるようですが、まだまだ狭い市場です。
仕事において、日本と比べニュージーランドでの方が自分には合っているのかもしれません。顧客の質の違いからくるものとしては、キウィのオープンな気風からかアイデアを出しやすく感じます。突飛なデザイン着想でも、顧客自身が良いと思えばそれで良いし、もし嫌なら嫌と言ってもらえます。日本人よりも、喜怒哀楽がはっきりしているので、こちらとしても顧客の顔色をうかがうというのではなく、素直に真摯にコミュニケーションを取ることを心がけています。
仕事の進め方も、ニュージーランドでは自由で伸び伸びして、自分の時間が掛けられると思いますが、その反面、仕事が取れないとなかなか生き残っていくのは難しいというのはあるかもしれませんね。それぞれに長短があると思います。
日本では縦社会で、大きい名のある会社に勤めないと認められない傾向があり、その大きい会社内でも歯車の一部のようで、企業の業務全体には関われないといったことがほとんどではないでしょうか。私はそういった大きな企業に属していましたが、自分の納得のいかないまま、時間に追われ、とりあえず次に進めなければいけないという状況が多くありました。しかし、こういったことで鍛えられたのか、こちらでの仕事に於いて、ちょっとやそっとの事じゃイライラすることはありませんね。夫はそういう経験がないためか、ちょっとのクライアントのわがままや、役所の申請がスムーズにいかなかったりすると、すぐにストレスを貯めてしまうみたいです。感じ方が違うんでしょうね。

極致は理想のマイホーム
一年程前にこの新しい我が家が完成しましたが、やはり着工から1年くらいかかっています。「家は3軒建てないと、気に入った家は作れない」とよく言われているのですが、私たちは時間を長くかけた分、少しずつ変更を入れることができ、最終的な食い違いもほとんどなく完成させることができました。
和風テイストを入れたいという夫の希望もあり、浴室は坪庭と外庭に一体感を持たせたセミジャパニーズスタイルとし、障子をイメージさせるリビングのパーテーションドア、玄関ドアもデザインしました。完全な和風ではなく、私達のデザインの主流であるナチュラルモダンを上手く溶け込むように工夫しました。
私は日本に住んでいた頃は、自国のトラディショナルなデザインにはあまり興味がなかったのですが、こちらに住んで仕事をし始めてから意識するようになりました。私が日本人の建築士ということで、デザインに「日本らしさ」を求めるお客さまは結構多いんです。1~2年に1度は帰省がてら日本を夫と旅行するのですが、ほとんど神社や古城などがある場所です。東京を拠点に電車で回るのですが、日本に住んでいた頃は見えなかったものが気になるようになりましたね。歴史的木造建築の美しさだったり、高層ビルなどを改めて凄いと思ったり。街は灰色の分量が多いなとか。いろんな意味で、日本に行くたび新しいアイデアが浮かんでくるんです。
この家はもちろん自分たちの理想を込めた家であるのですが、それと共にショーホームにもなるように作りました。床暖房システムをはじめ、家全体の構造体からインテリアの建築材料まで、自分たちが取引のある複数の会社それぞれ一押しのものを使用し、これが実際の見本となって活かされるよう考えてデザインされています。
心地よい自分の居場所
クライストチャーチに来て、はじめてのホームステイは70~80年代に断熱材なしで安く建てられたと思われる非常に古い家で、子供がジャンプすると底が抜けそうなくらいでした。「寒い」の一言が言えず、毎日セーターを着込んで寝ていたのを覚えています。
働きはじめてからは、小さなLDK+1ベッドルームを借りて兼オフィスとしていました。LDKは20帖程でとても狭かったのですが、そこには7年くらい住んでいました。
そして今はこのように、自分たちが思い描いて形にした自分たちの家で暮らし、仕事もしています。公私両方とも、自分の住まいでリラックスしていられるというのはとても幸せなことだと思います。理想とする場所に居られるこの心地良さを、今まで携わったお客様全てに何年も何十年も感じていてもらえたらこの上ない喜びですし、これからもそうできるよう妥協のない仕事をしていくのが理想ですね。
建築系の留学をしたい、体験したい、資格を取りたい、この分野で仕事をしたいと言う方はイーキューブ留学セクションまで、お問い合わせ下さい。お問い合わせはこちら
|