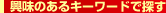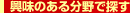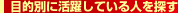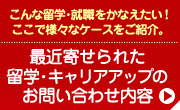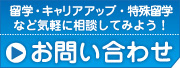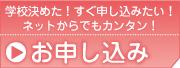|
ニュージーランド代表するハチミツの一つが「マヌカハニー」。 殺菌力が強い、胃の中のピロリ菌を退治してくれるなど、効果は多岐に渡っている。これらを科学的に実証し、「マヌカハニー」イコール「体にいい」という図式を磐石のものに仕立てたのがワイカト大学のモーラン教授である。しかし、マヌカハニーの成分はいまだ完全には解明されていない。この隠された謎を科学的な研究で解き明かしていく、モーラン教授はニュージーランドハニーのキーパーソンである。
 【Profile】
【Profile】
イギリス出身。母国ではリバプール大学で生物化学の研究を行う。ニュージーランドに移住後、ワイカト大学にて研究を続け、UMFの名づけ親としてNZハチミツ業界に名を馳せる。マヌカハニーとピロリ菌との関係性を立証したことでも名を知られている。学内にある彼が率いているHaney Research UnitはNew Zealand Honey Industry Trustの資金協力のもと95年に設立された。現在は医療の現場において有効な製品開発にも協力している。 |
マヌカハニーとの出会い
 私が母国のイギリスからニュージーランドに来て、ワイカト大学で働くようになったのは今から30年以上も前のことでした。もともとリバプール大学で生物化学を研究していたので、この国に来てからも、同じようなことができないかと探していました。農業大国ですので、酪農関係の職などを中心にあたっていたところに、偶然ワイカト大学での職があったのです。そこで私は再び生物化学を研究する機会を得たのでした。今でこそハチミツの研究という部分がクローズアップされていますが、私にとってのメインはアンチ・バクテリア「抗菌」に関することなのです。 私が母国のイギリスからニュージーランドに来て、ワイカト大学で働くようになったのは今から30年以上も前のことでした。もともとリバプール大学で生物化学を研究していたので、この国に来てからも、同じようなことができないかと探していました。農業大国ですので、酪農関係の職などを中心にあたっていたところに、偶然ワイカト大学での職があったのです。そこで私は再び生物化学を研究する機会を得たのでした。今でこそハチミツの研究という部分がクローズアップされていますが、私にとってのメインはアンチ・バクテリア「抗菌」に関することなのです。
よく、「どんなキッカケでマヌカハニーの抗菌性に気がついたのですか?」などと聞かれるのですが、これは私が発見し、気がついたのではありません。こういったことは私が研究する前から広く知られていたことです。ハチミツなどは古代から薬として使用されていますし、傷口の抗菌作用なども古くから言い伝えられています。それぞれの花によりその効果は違ってきます。もちろんマヌカハニーの効果にしても、一般的な知識としてあったのです。
特にマヌカの、植物としての特性はマオリの知恵の中や薬草学にも多く出てくることです。私たち科学者はそれらがどんな物質なのかをハッキリさせるための検証をしているのです。
私とマヌカハニーとの出会いも、そういった検証の場が始まりでした。抗菌作用の研究をしている中で、ニュージーランドにはマヌカハニーと言うものがあり、どうもそれは人間の体にある影響を与えている。その影響を与えている物質はなんなのか?それを検証することでマヌカハニーの効用が確信できる。そう思ったことでマヌカハニーの研究を始めたのでした。
マヌカハニーの歴史 
今ではニュージーランドで一般的になっているハチミツ、そしてマヌカハニーですが、この国ではどれくらい前から存在していたのかみなさんご存知ですか?先ほど申しましたようにマヌカという植物自体が人間に及ぼす影響は先住民族のマオリの人たちの知識の中にもありました。その中ではいろいろな効果が言われていますが、キーワードになっていたのは「清め」というものです。先祖からの知恵の中にマヌカはしっかりとありました。そうなると当然そのハチミツについてもマオリの人たちはなんらかの知識を持っていたと考えるのが普通でしょう。ところが彼らはマヌカハニーについては一切の知識を持っていなかったのです。なぜならハチミツという存在がなかったからなのです。
その理由は簡単です。西洋人が入植する前まではニュージーランドには巣をつくるハチがいなかったのです。すべて単体で行動するハチばかりだったので、ハチミツが作られることはなかったのです。ハチミツとマヌカとが合わさったマヌカハニーは研究する対象としては魅力的なものでした。なにしろ普通のハチミツよりも抗菌作用が強かったので、これはマヌカになにか秘密があるのではないだろうか?と考えました。
マヌカハニーの成分UMF 
こうしてマヌカハニーの抗菌作用を調べていくうちに一般的なハチミツに含まれている成分以外のものが入っていることがわかりました。それをUMF(Unique Manuka Factor、マヌカ特有の要素)と呼ぶことにしまし、UMFのテスト方法や数値化することを研究していったのです。
そしてこのUMFこそがマヌカハニーが他のハチミツと比べて優れている要因なのです。一般的なハチミツの抗菌作用は糖分によるものです。しかしこれは人体に入ると体内の酵素で中和されてしまいます。ところが「マヌカ特有の要素」はその影響を受けることはありませんでした。それだけでなく、熱にも強いことがわかりました。こうしたものが傷口のバクテリアを除去したり、胃の中のピロリ菌を抑制したりするのです。
少し気をつけて欲しいのですが、現在、このUMFが入っているハチミツのパッケージを見てみますとUFM10とかUFM20と表示されています。ただ、数値が10のものに対して、20のものはUMFが2倍入っており、その効果も2倍、という意味ではありません。たとえば、UFM8に含まれている抗菌物質の数値は100ですが、その7倍の700の物質が含まれているハチミツが示すUMFは27.5になります。
ハチミツの成分は複雑です。各成分の関係によって抗菌作用の力も変化します。ですから、UFMの数値がそのまま効き目の倍数、ということではないのです。現在のUMF数値の算出の方法はブドウ球菌の数値によるもので世界的に一般化された計算をしています。
UMFについて、それぞれが示す数値によって抗菌物質の含有量が変わってくると言いましたが、それでは何が原因となって変わってくるのでしょうか?また、どうやってその数値を人間の力で上げることは可能でしょうか?
まず、UMFの数値がなぜ違ってくるのかということについて、私のチームの調査結果を簡単にお話します。これはBee and Herbal New Zealand 社とComvita社の資金提供によって実現したものですが、ニュージ−ランド全土から新鮮なマヌカハニーを低温で保存したままを送ってもらいました。そして11の地区に分け、UMFの数値を測定したのです。結果としてやはり地域によって違いがありました。これは環境の違いが数字として現れたのだと思います。年間の平均気温、日照時間、土壌、水はけなどいろいろな要素があります。また、マヌカという木、そのものの違いもあることでしょう。同じマヌカと呼ばれている木でもいくつか種類があります。その生息分布にも関係していることが言えます。
こうした各地の自然環境がマヌカハニーのUMF値の違いを生じさせる要素の一つになるのですが、私はその他に、養蜂家のスキルも重要なファクターだと思っています。花から成分を採ってくるのはハチの仕事です。ただ、ハチに「あなたたちはマヌカの花だけから採取してください」と頼むわけにはいきません。巣箱の近くに他の花が咲いていれば当然そこにもハチは飛んでいきます。つまり、養蜂家が巣箱をどのタイミングで外に出して、ハチに採取活動をさせるかによってハチミツのなかのマヌカハニーの比率は変わってきます。開花の時期をうまく見計らうのは養蜂家の腕です。その腕があって初めて周りの環境が生かされるのです。
さて、UMFの数値を人間が上げることが可能か?ということですが、実はこれは可能なのです。私は今、数値は自然環境と養蜂家のスキルによって決まると申し上げたばかりですが、それ以外にもハチミツに熱を加えることでUMF値を上げることは可能なのです。あるいは暖かい場所に置いておくことも一つの方法です。先ほど全国のハチミツのデータを取るのに低温保存で送ってもらったといったのはこういった理由があるからです。そういった処理をした後のハチミツでは正確なデータを取ることができないからです。
熱を加えることでたしかにUMF数値はあがります。しかしその分、鮮度は落ちます。このようなハチミツは色が濃くなります。新鮮なハチミツはより明るい色をしています。
ニュージーランドハニーのこれから 
私は現在、抗菌作用の研究だけでなく、抗酸化、抗炎症、についての可能性を研究しています。ニュージーランドのネイティブの植物のハチミツの中にこれらの効果があり、すでに世に出ているハチミツに比べて、よりパワフルなものになる可能性を秘めているものがあるのです。できれば年内にはその成果を出していきたいと思っています。
ハチミツは一般的には食品となっています。ただ、昨今では医療の現場にもその効果が認められ、医療品としての活躍の場が広がっています。特に外傷などの傷口に対しての効き目は大きく、殺菌消毒薬としてはすでに製品化されており、チューブに入った塗り薬は薬局でも手に入れることができます。
またニュージーランドやイギリスの病院では布にマヌカハニーを薄く塗り傷口に当てる(湿布薬のようなもの)製品が使用されています。これらのバリエーションとして抗酸化、抗炎症の効果があるものは抗菌作用にも増して重要なことであると考えています。
ハチミツは自然の恩恵を受けたものです。自然環境が多いニュージーランドだからこそ可能なハチミツによる医療製品がどんどん世界で認められていくよう、研究を続けていこうと思っています。
留学したい、体験したい、資格を取りたい、この分野で仕事をしたいと言う方はイーキューブ留学セクション、イースクエアまでお問い合わせ下さい。
関連記事 蜂がもたらす物質の有効性は自分の身体が証明してくれています。
|