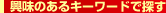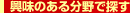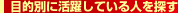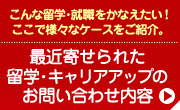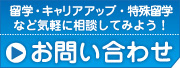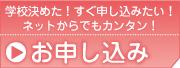|
テレビ、映画、コマーシャルなど、ニュージーランドには毎年、多くの撮影のグループが訪れる。そこでの通訳として汀さんは日本人のスタッフとキウイのスタッフの言葉をつないでいる。
 |
|
65年生まれ。神奈川県出身。明治学院大学フランス文学科卒。在学中はダイビングに夢中になりインストラクターの免許を取得する。卒業後すぐにNZへ留学し秘書の勉強をする。K’Rd.にある雑貨店「iko iko」のマネージャーとして95年にNZに戻る。その後「Zena」(ジーナ)の通訳として約2ヶ月弱、撮影関連の仕事を始める。
|
英語との関わり
中学生の頃は学校の授業の中で英語が好きでした。そのため高校は普通科ではなく、貿易外語科に進みました。ところが、その学科は英語が好きで、英語が得意な人ばかりが集まってくる科でした。帰国子女も多く在籍しており、たちまち、私は英語の落ちこぼれになってしまいました。それでも、週に10時間以上は英語の授業があり、毎日のように小テストが行われていました。私にとっては、仕方なくという言葉があてはまるのでしょうか、それらをクリアするために勉強をしていました。
特にグラマーを必死に覚えた記憶が残っています。英文法の本に出てくる例文はすべて覚えました。単語カードに書き出して、電車に揺られながらそれをめくっている時の記憶が蘇ってきます。例文に出てくるのは全て基本のフレーズです。何度も繰り返し読むことによりそれを音として頭に入れていました。私は自分が語学の才能を持っている人間ではないと思っています。そのために基本をしっかり押さえる必要がありました。この方法は私が英語を習得する中でキーとなる覚え方でした。
私の学科では第二外国語がありました。私はフランス語を選択しており、英語が嫌いになった私はフランス語に力を入れるようになりました。それで大学もフランス文学科に行くことにしました。
英語の習得1
ニュージーランドに初めて来たのは86年のことでした。学生としてオークランドの秘書の学校に一年半通いました。今のポリテクに近い感じの学校です。学生時代はずっとフランス語に傾倒してきましたが、卒業を機に英語を、もう一度やってみようと思ったのです。ただ、英語だけを学ぶことは考えていませんでした。私が英語を得るならば、何か他の目標があった方がいいと考えて、セクレタリーコースに通い、秘書の勉強をすることにしました。
ところが、これが大変でした。こちらに来た当初は先生が話していることがなかなか聞き取れませんでした。授業の内容はオフィスワークやタイピング、リーディング、ライティングなどでした。
やっと慣れてきた頃には授業は急速に難しくなっていました。特に私が苦手だったのはショートハンド、速記でした。学校ではピットマンという方法を教えてもらっており、これは相手が話す音を拾い、それを書き留めていく方法でした。当然ここでは私達日本人が最も不得意とする、sとthの違いやRとLの違いを聞き取らなければなりません。意識すればするほど、迷いが出てきます。sなのかthなのか?RなのかLなのか?速記の時間は頭の中がクエスチョンマークでいっぱいになっていました。ここでも何度も繰り返し聞き、自然に聞き取れるようにするしか方法はありませんでした。
学校から帰ればすぐに机に向かっていました。宿題が毎日、山のように出されていたのです。そのためそれらに追われることが多く、予習に費やす時間はほとんどなく、復習が少しできるくらいで、それ以外は宿題に必死に取り組んでいました。
特に苦手な速記の宿題では、レポート用紙に半分も満たない量の文でも、何度もテープを聞きました。これと似た感じの宿題ではタイピングがあり、これもまた、テープを聞いて、タイプを打っていくというものでした。
耳で聞いて、それを英語で書く。当時の私にとっては苦しいものでしたが、これもまた、基本の練習だったのでしょう。繰り返し行うことによって身に付いたような気がします。日本に帰ったときに弟が空港に車で迎えに来てくれていたのですが、その車の中で聞いたFENがスラスラわかるようになっていました。
英語の習得2
その後はしばらくの間、日本で働きました。私が勤めたところは企業研修や海外研修を企画したり、サポートする会社でした。そこでは海外から語学研修の指導をする先生を招き、一緒に相手の会社に行き、カリキュラムや教材開発のミーティングを行っていました。その際に私はコーディネイターとして中に入りました。また、先生のリクルートもしていました。クライアントの企業からはいろいろなリクエストが来ます。イギリス系の英語がいいとかアメリカ系の英語がいいとか、また単にネイティブスピーカーというだけでなく、専門知識を持った人が要求される場合が多く、例えば製薬会社の研修の場合は、その業界で働いていた人や、薬学部などを卒業している人などが求められていました。そういったニーズに合う人をアメリカやイギリスでコンタクトを取り、日本へ来る場合の条件などを取り付けていました。
そして95年に再びニュージーランドで生活することになりました。ウェリントンで雑貨店をしていた友人が、オークランドでも店を開くことになり、私はその店のマネージャーとして来ることになったのです。連絡を受けたのはオープンの2ヶ月前のことと、急な話だったため、オークランドに到着して3日目には私はお店に立っていました。
お店では全ての商品を覚えることから始まり、一つ一つのことをこなしていくことで無我夢中でした。お客さんや仕入れの業者さんからの信頼を得るために些細なことでも丁寧に対応することを心がけていました。
言葉の面でも同じです。私達アジア人の英語はクセがあります。にもかかわらず、ネイティブぶって話をすれば相手は怪訝そうな顔をして、理解してくれないこともあります。そこで、私の場合は相手によっては、先に「ごめんなさいね、私の英語わかる?」と言ってしまうことにしていました。すると相手は「大丈夫よ、ちゃんとわかるわよ」と返してくれる場合が多く、その後のコミュニケーションが円滑に進みます。英語を喋ることが目的ではなく、お客様に商品を買ってもらうことが目的でしたので、うまく喋ろうとはせずに、相手にわかってもらえるように努力していました。無理に背伸びをしないことが相手との距離を縮めることになり、話に膨らみを持たせることになります。そして結果的に英語の言い回しを覚えることにもつながりました。
ただ、最初の頃は失敗もありました。私が当時、苦手だったのは電話です。相手の顔が見えずに、言葉だけで伝えなければならないのはどうも調子が狂ってしまいます。お客さんからの注文の電話で、お互いに話をしている商品がまったく違うモノだったということもありました。おまけにそれをお客様に送ってしまったこともあります。
それでも多くの人と会い、色々な英語を聞く機会はListeningやSpeakingには非常に役に立ちました。これらのことは、高校生のときにしていた、音として頭に入れることと方法は同じだと思っています。繰り返すことが大切で、その結果として多くのフレーズが頭の中に入ってきました。また、繰り返すと言うことでは、新聞を読むことを毎日の習慣にしていました。自分の興味がある場所から読んでいけば長く続けられます。また読むことで会話のときの話題にもなります。
仕事としての英語
ある日、キウイの友人から仕事を頼まれたことがありました。その内容はテレビの撮影で日本人のエキストラが大勢集まるため、その衣装合わせや、オーディションまた実際の撮影時の通訳をすることでした。そこでは撮影をする上で使われる独特の言葉を覚えていくことが非常におもしろい作業でした。例えば call time、これはセットなどの撮影する場所に入っていなければならない時間のことです。また、Move backgroundという言葉を初めて聞いたときは、どういう意味で使われたのかよく理解できませんでした。ここではbackgroundは画面での背景ではなく、後ろの人たち、つまりエキストラの人を示す言葉で使われていました。エキストラの人は移動してくださいという意味になるのです。反対に、俳優さんや女優さんなど、演技をしている人たちをforegroundと言っていました。この時は多くの日本の人たちと一緒でした。エキストラといえども日本人はしっかり動いていました。撮影が夜になることも多々ありましたが、そんなときでもダラダラする人はおらず、他のスタッフからも好評でした。
その後はCM等の撮影でも通訳として入りました。日本の家電メーカーやビール会社、自動車メーカー、たばこ会社などがニュージーランドで撮影をしています。こういった撮影は日本から直接入ってくるだけでなく、アメリカから来る場合もあります。そのような場合はスタッフはアメリカ人、日本人、そしてキウイとなります。そして現在は「The Last Samurai」の衣装部の通訳をしています。日本での撮影に立ち会いましたし、今後はタラナキにも行く予定です。
ドラマや映画撮影での通訳は単に英語から日本語、日本語から英語と、言葉だけを訳していたのでは相手に意味が通じません。撮影されているストーリーの文化的、時代的背景の知識がなければ、私自身が意味を取ることができませんし、そうなれば当然、相手に伝えることはできません。私たちの国では、家に上がるときに靴を脱ぐのが常識ですが、そうでない国もあります。日本のことでも地方によって、また現代と過去では言葉も服装も違ってきます。そのため、1本の仕事が終わったからといって、次の仕事も同じようにできるわけではなく、毎回、新しい知識を入れていかなければなりません。
ですから、現在は、単純に英単語や文法の知識を増やしていくのではなく、日本やその他の文化や習慣を学んでいくということも、英語を使う上で大切なことになっています。私が関わっている通訳では、言葉を交わすお互いの目的や、それぞれの国の習慣などを頭において、その言葉を発する人の気持ちも同時に訳していくことが大切だと思っています。
小澤 汀さんの英語上達ポイント
1. 文法の参考書の例文をすべて暗記した
2. テープを聞いてそれをすばやく書き取れるようにした
3. 上手に話そうとせずに、理解して貰うことを頭に入れて会話 をした。その結果、相手は気をよくして、話しが膨らんだ。
4. 1~3までのことはすべて繰り返して行った。
留学したい、体験したい、資格を取りたい、この分野で仕事をしたいと言う方はイーキューブ留学セクションまで、お問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
|