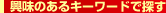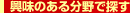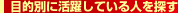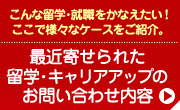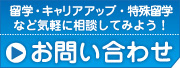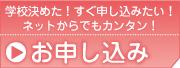Vol.69 自由時間 ニュージーランドで高校留学、そして幼児教育コースへ |
|
英語好きの母親の影響で、小さい頃から英語環境にいたという大庭玲於奈さん。ニュージーランドの高校に留学、そして卒業後、まだまだ勉強を続けたいという思いに駆られ、今年3月からWhitireiaポリテクニックの幼児教育準学士コースに進学した。学究肌で、勉強中心の日々を送っている玲於奈さんに、ニュージーランドでの学生生活について伺った
 |
1988年生まれ。静岡県出身。日本の中学校を卒業後、Auckland Girls Grammar Schoolで3年間就学。2007年3月よりフィティレイアの幼児教育準学士号Level 5へ。研修時、毎日園児たちから「どうして?」「なんで?」の質問攻めにあって以来、自分でも考察する事が趣味のようになっているのだとか。園児の質問といえどもその内容は濃く、自然科学や異文化の謎(言語、地域、人、植物など)についてで非常にアカデミック。 |
すでに視野にあった高校留学
静岡の中学校を卒業後、ニュージーランドへ来て以来すでに3年半を学生として過ごしている玲於奈さん。まずは、これまでの経緯を伺った。
「まずは、オークランド・ガールズ・グラマースクール(Auckland Girls Grammar School)に入学し、そこで日本の高校の修学期間に当たるYear11、12、13の3年間を過ごしました。留学に興味を持ちはじめたのは、もともとお母さんが英語好きでオーストラリアへの留学経験があったことがきっかけなのかもしれません。その留学後も、オーストラリアを始め、いろいろな国を旅行してきたお母さんの影響で、私も自然にいつかは留学してみたいと思うようになっていました。」
玲於奈さんは、幼稚園に通っている頃から英語の教材を与えられたり、マンツーマンの英語教室に通ったりと、彼女の母親が積極的に英語環境に身を置かせてくれた。中学校では、玲於奈さんのクラスを担当した英語教師がイギリスで学んだと言いつつも実際使う英語がアメリカンイングリッシュだったのが気になり、その頃からクイーンズイングリッシュをもっとちゃんと学びたいと思い始めるようになった。玲於奈さんと彼女の母親で、英語圏のいろんな国へ旅行で訪れてはいたが、二人とも唯一行ったことがなかったのがニュージーランドだったため、この国の学校を留学先にしようと決意した。
玲於奈さんが学んだオークランド・ガールズ・グラマースクールは生徒数が1200名を超え、生徒の国籍は約50カ国、教師の国籍まで合わせると約60カ国に上るという。もちろん、当初はなかなか英語が聞き取れなかったが、英語に親しむことは小さな頃からしていたので、慣れるために長い間苦しむことはなかったそうだ。 Year11、12、13で学んだという科目を挙げてみよう。数学、地理、法律学、経済学、自然科学、ツーリズム(Level 2、 3)、Service Sector(サービス業)、チャイルドケア(Level 2)、アート、デザイン、家庭科などと多岐にわたる。高校留学を終えた日本の留学生は、日本に帰って大学入試といった選択をする学生が多いが、玲於奈さんがニュージーランドに残り、進学して勉強を続けるという選択をとったのは以下のような理由からだ。
「3年間英語圏で勉強はしたけれども、もし卒業後、日本へ戻り、大学に行って就職して…となったら絶対に英語の感覚を忘れてしまうと思ったんです。せっかくニュージーランドで高校のうちからさまざまな分野を勉強できたので、それを生かしてさらに高度な勉強をしたいという気持ちになっていました。」
ニュージーランドでの生活で幼児教育への関心が深まった
進学先に決めたのは、Whitireiaポリテクニック(以下、フィティレイア)の幼児教育準学士コース(Diploma in Early Childhood Education Level 5)。
「フィティレイアを選んだ理由は、内容はハードだと思ったけれども1年間という短期間でディプロマを取れるところが魅力でした。ポリテクニックは国立の高等教育機関だし、ほぼ大学と同レベルの実務大学と捉えられています。高校時代に勉強したチャイルドケアはLevel2で、このフィティレイアのコースはそれよりもかなりハイレベルの内容です。このLevelというのはNZQA(New Zealand Qualifications Authority ニュージーランド教育資格審議会)が制定している資格で、学校を変更してもこのLevelにより履修内容は一貫性があるんです。」
玲於奈さんが幼児教育を専門的に勉強し始めるまでには、これまでのニュージーランド生活全てが糸口となっていた。初めてこの国に来てホームステイをした家庭では、ホストファザー、マザーに彼らの子供と同等に厳しくされ、時には涙することもあった。でも、これは愛あるお叱りだったと分かり、今ではとてもありがたく思っているそう。そして、1人っ子の玲於奈さんの初めてのホストブラザーとシスターはだいぶ年下で、ホームステイ2年目にはベビーシッターを任せてもらえるまでになった。この経験が、親に対しては子供として、子供に対しては年上のお姉さんとして、家庭内で自然と養われるべき「立場を考えての接し方」というものを改めて学ぶことができたという。 3年目にホームステイ先が変わったが、この家庭でも5歳の男の子、8歳と11歳の女の子二人の計三人の子供たちがいた。前の家庭は二人の子供だったが、ここは三人のせいか子供たちの中で形成されている人間関係がとても興味深かったという。基本的にはみんな無邪気だったが、一番下の男の子はマイペースで女の子が口喧嘩していても気にしない。妹は口が達者でしたたか、物静かで寡黙なのは姉、という典型的な光景を目にした。
教育法を知って、それをどう与えていくか
このようにいろいろな要素が幼児教育への関心を生み、今年3月以来このコースへ在籍している。有名な教育法やSelf and Children、Human Developmentなどをメインカリキュラムとしており、具体的には理論を学んだりさまざまな学問を研究したり、そして現場のリサーチをすることによって、自分が学んだことが自身の教育にどう反映していくかといったことを認識していく。
「有名な教育法とは、ルドルフ・スタイナーやマリア・モンテッソーリなど人物が推奨するものやレッジョ・エミリアなど地域から発祥しているものなどいろんなものがあるんです。このような勉強は基本的なことのように聞こえますが、インターンシップや就職先としてプレスクールやプレイセンター(以下センター、親によるボランティア運営の幼稚園・保育園のような場所)を決めるためにはしっかり理解しておく必要があります。というのもニュージーランドのプレスクールやセンターでは、それぞれが推奨する教育法をもっており、それらのほとんどは有名な教育法に基づいているからなんです。履修の中で、こういったいろんな教育法を比較し、自分のセンターを作った場合のデモンストレーションなども行ったりします。コミュニケーション技術の勉強の一環として、実際センターでインターンシップを行った事があるんですが、その時にこんなことがありました。そこでは2~5歳までの子供が学んでいたのですが、全ての子供たちが使っている言語は英語にもかかわらず、子供たちが何となく作るグループは同じ国籍同士(同じような外見同士)なんです。視覚による親近感といったものが、自覚なしに現れるというのは幼児心理を知る上でとても興味深かったです。多国籍文化ならではの教育現場だし、このようなニュージーランドのプレスクールやセンターで学ぶことは、成長すると共に、多様性、文化/宗教などの価値観の違いを理解する能力を自然と身に付ける事ができるのではないでしょうか。」
ニュージーランドでは、教育者は機会を子供に与えるのみで、何をしたいのかという意欲は、子供自ら引き出させようとするレッジョ・エミリア系のセンターが多いという。それとは対極に、子供が勉強する事を教育者が予めして準備しておくのがモンテッソーリ系で、玲於奈さん自身の考えでは、どちらかといえばモンテッソーリ系だと思ったそうだ。
「やはり、お母さんが教育に関心を持ち続け、私が小さな頃から私の将来を考えて学ぶべきものを与えてくれた事をとても感謝しています。そして将来は、自分がしてもらったことを自分の子供にも同じようにしてあげたいと今は思っているんですが、これは自然な成り行きなんでしょうね。」
知識、技術だけではなく人として向上したい
「小さな子供と接するのに一番大切なことは観察する事。そして目線を合わせて相手の気持ちになってあげること。そして、レベルは合わせつつも常にサポートするのを忘れてはいけないことを学びました。そして、そうなるためには、まずは自分を知る事。自分の行動観察をすることから始まりますが、これは心理学の基本中の基本でもあります。」
コース内容には200時間もの実技研修が含まれており、フィティレイアによってオークランドにある400以上のプレスクールやセンターの中から、自分のレベルや条件に合う場所を紹介してもらうことができるという。といっても勉強期間が1年の学生には、見学は可能だけれど、なかなかの狭き門だそうだ。
「私もそうでしたが、一般の方にとってチャイルドケアというのは一見簡単そうに感じると思うんです。しかし、実際は大人を相手にする以上に高いコミュニケーション能力を必要とされる。これから、今年12月に準学士コースを修了した後、さらに学士コースに進んで勉強を続けていけば、体験できるプレスクール、センターも増え経験を積むことができると考えています。でも、社会人としての経験を積むことは教育者としても大切な事だと思うので、学生は一旦終了して働いてみたいという気持ちもあるんですよね。どちらにしても、常に学ぶ気持ちを忘れず、教育者となる前にまずは人としてのレベルを上げていきたいです。」
ニュージーランドへ高校留学したい、幼児教育を学ぶ留学をしたい、体験したい、資格を取りたい、この分野で仕事をしたいと言う方はイーキューブ留学セクション、イースクエアまでお問い合わせ下さい。
|