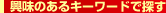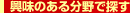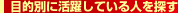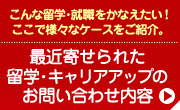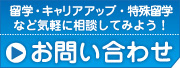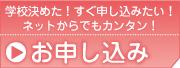|
患者が医者の説明を理解していなければ、医者は自分の義務を果たしたことにはならない。そのため、ニュージーランドの公立の病院では、英語に自信のない患者に通訳の手配を行っている。そこで政府公認の資格を持つ通訳としてドクターと患者の間に生ずる言葉の誤解をなくす役目を果たしている涼子さんは、英語に自信がある人でも医療通訳を要求した方がいいと言う。自分自身あるいは親族が病気の場合は普段の冷静さを欠くこともあり、病院での言葉のミスは後で大きな間違いにつながる可能性があるからだ。
 |
|
茨城県出身。ニュージーランドへ来たのは1971年。この国での仕事は皿洗いから始まり、カフェの店員、免税店、映画館の案内嬢、ツアーガイドでの通訳、日本語教師、領事館職員など多数。日本語教師は高校の Evening classで10年に渡り教鞭をとる。こうした仕事と子育てを通して英語を学び、93年にHealthcare Interpretingの資格を取得して医療通訳を始める。その後すぐに法廷での通訳業務も開始する。
|
当初の英語
私がニュージーランドに来たのは71年のことです。一般のサラリーマンの平均月給が3、4万円の時代に片道40万のチケットを買って飛行機に乗りました。この国を選んだのは姉の知り合いがオークランドに住んでいたためです。
こちらに来てすぐに知人に、wards maidとして病院で皿洗いや、床掃除をする仕事を紹介してもらいました。今ではこんな好条件はまずありませんが、当時は病院が人手の不足を補うために、朝昼晩の食事とアコモデーション付きで看護婦やメイドを雇っていました。私はその優遇されたアルバイトに就き、一日中英語の中にさらされることになりました。もちろん職場には日本人は誰もいません。職場どころかオークランドの街でも、私が知っている限りで日本人は14~15人しかいませんでした。同僚はキウイだけでなくカナダ、オーストラリア、アイルランド、サモア、トンガなど様々な国の人でした。その中には働きながら看護婦の勉強をしている人もいましたし、60歳のオーストラリア人のおばあちゃんもいました。
私も海外に出れば、英語ぐらいは話せるようになるだろうと思っていた一人でした。ですから日本では特別に英語を勉強していたわけではありません。そのため、こちらに来て初めは相手の言っていることがわかりませんでした。英語を勉強するというより病院での仕事や、仲間や、生活に慣れることで精一杯でした。
習得方法
本気で英語の勉強をする気になったのは相手の言っていることを理解し、自分の言いたいこともほぼ言えるようになった頃、ニュージーランドに来て3年経ってからでした。今まで、やっておけばよかったと思うことを実行していきました。とはいっても内容はシンプルです。
本を読むこと、新聞を読むこと。そして単語ノートを作り、まずはボキャブラリーを増やすことを心がけました。特に効果的だったことは本を読むことでした。当時の私のような英語の初心者が、本を読むことはなかなか大変なことです。それだけに、最初の一冊を読み切ったときは英語に対しての取り組みが大きく変わりました。それまであった苦手意識の壁のようなものが取れたのです。
読み始めた頃は、一行ひっかかればそこで立ち止まって考えていましたが、それよりまず読み終えることを第一にし、その代わりにわからない単語はすべて書き留めました。
ノートは見開きの両ページを使います。左のページには単語とその意味、右ページにはその単語の出てきたセンテンスを書きました。ノート一冊を早く埋めることには心理的な達成感がありますし、後で見返すときに読みやすいように単語と単語の間はダブルスペースにしました。そしてその単語帳を使って、もう一度その本を読み返し、そのときに覚えていない単語をカードにしました。A4の紙を16等分して一枚ずつの右と左に単語と意味を書きます。これをひとつかみ20 枚なリ30枚なりを片手に持ちます。英語の方か日本語の方か半分を隠しながら意味や単語を思いだしながらめくっていきます。覚えたのは捨てて、新しい言葉を順次補給します。単語を覚えるというのは、あまり思弁的なことではなく、むしろ機械的な作業ですから、単純ながら、やるかやらないかだけが結果を左右します。
私の場合、ラジオもよく聞きました。聞くだけでなくカセットにとって繰り返し耳にしました。私が来た当時はテレビのチャンネルは1つだけ、放送時間そのものも短かったため、勉強に結びつくほど観ることはできませんでした。ですからラジオのドラマは楽しみの1つでした。これも1回目は十分に聞き取れません。2、3回聞くと意味が取れるようになり、5、6回で一つ一つの単語が聞き分けられます。30分か60分のテープを家事をしながら最低 10回は聞いていました。
私は辺りの人、誰にでも、ものを聞きたずねることは好きではありません。これは個人的な好みの問題ですが、顔見知り、同僚、友人は教師ではありませんし、答えを見つけるのは自分です。人を頼りにしまいと思っていましたのでわからないことは電話帳くらいある大きな辞書で調べていました。これらのことは非常に手間がかかり、時間もかかることです。しかし確実に英語を覚えていく道だと思います。
人に聞いて安直に答えが返ってくると思っているうちは周りに知識を求めているのでしょう。そんな人は多分単語帳を作る手間をかけたりはしないでしょう。
ニュージーランドに来て5年目くらいで、十分に自分の言いたいことが伝えられるようになったと思っていましたが、普通に会話ができるようになったのは10 年くらい経ってからだと思います。しかし、20年経ってみたら、10年前には大したことは話していなかったと感じました。
その後、ツアーガイドとして通訳の仕事をしました。また、子育てで、学校に行き他の子の親と話をしたり、話し好きな夫との日々の長時間の会話が英語の勉強になりました。
ただ、医療通訳になるためにはそれだけでは到底無理です。ラジオを聞きながらその場で理解していく。新聞や『TIME』を目で追いながら即理解する。英語だけのことを考えた場合にはそこが医療通訳へのスタートラインです。例えば、折り紙で鶴を折る説明を言葉だけでしてみてください。日本語でも少しややこしいことになりますよね。それに類似した状況はいくらでもあります。「右手を上にあげて、そのまま自然に左の下の方に動かしてみてください」といった類。そして単なる名詞の羅列ではなく、抽象的な内容の会話をしなくてはならない場合もあります。こういったことを瞬時に正確に伝える必要があります。
医療の通訳ですからスピードも大切です。右手をどうこうというのはまだしも、緊急を要する場合にはわずか数秒の時間差でもドクターや患者のストレスになります。 また、相手の言っていることを99パーセント理解しているだけでは、病院で通訳をするのは危険です。人の一生や、生命に関わる体のことだからです。日常生活では絶対に使わない医療単語も当然必要になりますので、私の場合はAIT(現AUT)の12ヶ月の通訳養成コースに通いました。まず、そこで Healthcare Interpretingの資格を取りました。その後、医療用語のコースであるMedical Terminologyのコースも取りました。
ここはオークランドでは唯一、ニュージーランド政府公認の資格が取得できる学校です。これらのコースは英語を勉強するものではありません。医療通訳としてのテクニックの基礎を身につけるコースです。当然、講義は英語で進められます。それが普通に理解できなければ通訳以前の話になってしまいます。ベースに英語があり、そして通訳としての技術、その上で、英語と日本語で理解する医療知識を身につけるのです。もちろんそれだけでは不十分ですから、色々な資料を読み漁りました。そして93年から医療通訳の仕事を始めたのです。
仕事での英語
オークランドで公的な医療通訳の派遣サービスが始まったのは確か90年前後だったかと思います。初めはSouth Auckland Healthというオークランドの南のミドルモア病院などを統括している医療や病院の組織がInterpreting and Translation Service (ITS)という部門を作り、スタートさせました。その後、99年からシティを中心としたa+(エイプラス)のPublic Healthが通訳サービスを開始。ここはオークランド病院、グリーンレーン病院が所属しています。去年からはノースショア病院、ヘンダーソン病院など北部、西部を管轄しているWaitemata HealthのAsian Health Supportにも通訳部門が開設されました。
通訳サービスが始まった当初はオークランド病院やノースショア病院など他の組織の病院にもITS が通訳を派遣する形を取っていましたが、現在ではそれぞれの地域の組織が独自の通訳の部門を持っています。私達は各組織の通訳部門に登録されており、病院から要請があった場合はそこから派遣されることになります。
永住者の場合、公立の病院(Hospital)では費用は国、つまり病院の各病棟の負担になります。また旅行者の場合ですと旅行保険に加入されている方はその保険が適応されますので、誰でも言葉の面で心配する必要がないようになっています。
私立の医療機関の場合は基本的に、患者さん個人と通訳の間の契約ということになりますので、通訳の費用は各個人の負担になります。ただし、旅行者の場合は海外旅行保険で対応できる場合がほとんどです。
医療現場での通訳の仕事は英語と日本語の交換と言う作業です。基本的に通訳は通訳以外のことをしてはいけません。
でも看護士さんと世間話をして、この患者さんはあなたにお礼を言ってます、あるいは隣のベッドの患者さんに、退院おめでとうと言っていますよと伝えてあげたりと、日常的な会話を手伝うこともあります。それは患者さんが気を楽にしていられるためには必要なことだと思います。
どんな仕事でも同じだと思いますが相手のことを思いやる気持も大切なことです。特に病院に来ること自体、普通のことではありません。患者さんやその家族は大きな不安を抱えています。病気や怪我そのもののことだけでなく、家族のこと、これからの生活のこと、仕事のことなども同時に考えています。それに加えて、言葉の面での不安です。
こういったことを十分に理解して、思いやりの気持を持って接することも私にとっては通訳と同じくらい重要なことだと思っています。
仕事での英語2
仕事の中では、日本人とキウイの様々な習慣の違いを感じることもあります。患者さんから多い質問では「薬はお茶で飲んでもいいですか」というもの。そのまま訳すと、キウイのドクターはなぜわざわざ聞くのか怪訝そうなので、生活習慣を説明して答えをもらっています。
ドクターにあまり質問をしない方も多いように感じます。説明終了後、医者は必ず「なにか質問はありますか?」と聞きます。それに対してほとんどの人が「いや、大丈夫です」と答えます。なぜか本当にこの言葉を使う人が多いのです。そしてその後の行動もほぼ一緒です。ドクターが部屋を出た後に、私に「あのー」という言葉で質問が始まります。私は医者ではないので、残念ながらそれらの質問に答えることはできません。もう一度、スタッフを捕まえるか、質問を紙に書いておいてもらうようにします。
また、アジア系の人は会話をしていると、理解していてもいなくても、うなずくことが多いようです。これは病院では良いことではありません。わからないまま、うなずいているとドクターや看護士は患者が理解していると勘違いしてしまいます。うなずいている時、あなたは言葉を使っているわけではないのです。うなずくなどのボディーランゲージはコミュニケーションで案外、大きな比重を占めているのですが、解釈は文化によって違います。日本での『ハイハイ、聞いてますよ』の感覚でうなずいていると、同意している、理解していると解釈されてしまいます。
病名がハッキリ知りたいと言う患者さんも多いです。こちらのドクターの特徴として病気や怪我の状況や対応の説明は充分すぎるほどしますが、習慣として病名の特定をしないことが多いです。ある患者さんが「病名がわかると、原因がわかるので、気持の上で少し安心する」と言っていたのですが、こちらのドクターにはその発想はあまり見受けられません。病名を知りたい方は質問のときに聞くのがいいと思います。
病院での通訳と同時に私は裁判所や警察での通訳もしており、病院同様、慎重な対応が求められます。
私達が普段、日本語を話すときは主語を言わないことが多く、そのため聞き返さなくてはならないのには困ります。「行きました、見ました」の主語が、We, He, Sheのいずれであるかは、文脈からわかっても確かめないと、話している当人の突拍子もない発想が背景にあったりしますから駄目押しをしながら訳さないといけません。特に裁判での通訳で「そこへ行ったことは、その時は知りませんでした」と言われても訳すのに困ってしまいます。動作をしている対象者が一人で、時間や場所もある一点だけのことであれば、問題はありません。しかし、たいていは、何人も対象者がいますし、時間や場所も一点だけではありません。そのため、いつ、誰が、どこへ、ということを、私が聞かなくては正確に伝えられない場合が生じてきます。すると日本語がわからない人はどうして通訳の人間は英語に訳さずに、日本語で会話をしているんだ、なにかアドバイスでもしているのではないかと思ってしまいます。
こういったケースがあまりにも多いために、最近ではあらかじめ裁判長には聞き返すことがあることを説明しておきますが、それでも日本語のわからない人たちにとっては疑わしく見えるらしく、弁護士に今の訳は何だと聞かれたり、なぜ証人と会話を交わすのかと追求されたりということもあります。
英語を話す上では、文法的に正しい日本語を理解していることがベースになります。それでなければ英語でも文章が成り立たないことを私達は認識する必要があります。
公立の病院では誰でも通訳を頼むことができますが、その通訳が不十分であると思ったら、別の通訳に代えてもらう、あるいは、次回に他の通訳にしてもらうことも可能です。 誰だって、もし手術ということになって、その同意書にサインをするのにしっかりとした意味もわからずに自分の名前を書きたくないと思います。ですから、あなたの権利として通訳を頼み、言葉の面での不安は取り除いてください。そのために私達がいるのです。
現在は、インターネットで医療関連のサイトを見て最新情報を入手しています。毎日のように見ていないとすぐに新しい英単語が出てきますのでチェックは欠かせません。また、今でも単語カードを使っての勉強は続けています。覚えた単語でも使わないと忘れてしまうことがあります。常に繰り返すことにより、いつでも頭の中から単語が出てくる状態にしているのです。英語はまだまだ勉強だと思っています。
涼子さんの英語上達ポイント
1. 新聞、雑誌、本を読み単語帳をつくる。
2. 読む過程で単語帳を作る。
3. 更に単語カードを作り、時間を作ってカードをめくり読む。
4. ラジオを録音し10回以上、同じモノを聞く
通訳や翻訳家になるための留学をしたい、体験したい、資格を取りたい、この分野で仕事をしたいと言う方はイーキューブ留学セクションまで、お問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら
|